最終更新日 2025.6.23. by fukufukuyama
「どうしてもっと早く、病気に気づいてあげられなかったのだろう」
「どうしてもっと一緒に居られる時間を作らなかったのだろう」
「どうして最期に一緒にいてあげられなかったのだろう」
「どうして長生きさせてあげられなかったのだろう」
どうして・・・どうして・・・と、大切な家族の一員を見送ったあとのペットロス心にモヤモヤと暗い影が漂っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中には、不慮の事故や飼育中の不注意によってペットの死を「自分のせい」と思ってしまう状況になっているかたもいらっしゃるかもしれません。

このページでは、私自身がこれまで2匹の愛犬を見送り、そして「ペットのおくりびと」として数千件のご家族様の大切なペットちゃんの葬儀をお手伝いしてきた経験から感じた学びやメッセージを綴っていきたいと思います。
ペットロスの中で読むのがつらいこともあるかと思いますが、ペットの死後私たち家族がどうその出来事と向き合っていくか、1つの考え方のお手伝いになればと願っています。
ペットロスの心に絡みつく「後悔」は誰にでもある
私が実際にペットちゃんたちの旅立ちのお見送りをしている中で、「できる限りのことはしてきたので、後悔はしていません」とはっきり断言をされたご家族様は、私がこれまで出会った数千組のご家族様の中でもたった2組くらいだったかと思います。
みなさん、どんなに時間と体力と精神力、そして自身の生活費を削りながら動物病院への医療費をかけて、心身ともに寄り添い続けていても「もう少しできたことがあったのでは」と後悔をなさっています。お話を聞く限り、誰もができることではない大変な労力をかけていても、です。
後悔をしていないとおっしゃるご家族様の背景には「普段はお留守番が多かったけれど、コロナ渦で在宅ワークも多かったので最期はずっと一緒に居られたから」「動物病院の先生に本当に良くしていただいたから」と、社会的な背景でペットと過ごす時間が増えたことや、自分自身がペットちゃんのためにできることをできたという達成感、周りの方の協力に感謝をする気持ちによるもので、悔いはないとおっしゃる理由も様々でした。
ペットの死後、どうして後悔が残ってしまうのか

誰しも、愛するペットたちが最期に苦しまないよう、できるだけ身体がしんどくないように生きてほしいと、ベストを尽くしたい気持ちでいることと思います。最善最良の医療を受けさせてあげたい、仕事なんかそっちのけでもいいからこの子と一緒にいる時間を作りたい、できることなら自分の命の時間を削ってでもこの子に分けてあげたい、と。
それでも、私たちには日常というリアルな生活があり、思うように動物病院に通わせる時間や費用をかけられなかったり、どうしても仕事に行かなくてはいけなかったりと、愛情以外でその子に注げるものには限りがある場合が多いです。
また、「〇〇さんのお家はこうしていた」「〇〇ちゃんのママはこうできていた」「〇〇ちゃんはもっと長生きしていた」など、誰かと比較することで自分では成し遂げられなかったことが後悔として残ってしまう場合もあります。
でも、一度振り返ってみてもらいたいのです。
「その時に自分ができるベストのこと」を、皆様はやっていたのではないでしょうか?
誰かと比べて、より手厚くしている人に劣等感を感じる必要はありません。きっとペットちゃんたちには、家族の方がお世話や看病をさぼっていたようには映っていないと思います。もちろん、日々続く看病や介護の中で、誰しもお互いから少し離れて息抜きをする時間も必要です。時々お買い物に出かけたり、安心してぐっすり眠っている間を見計らって一息つきに行ったり、そういうちょっとホッとする時間は必要です。ずっとエンジン全開で看病をし続けるということはできません。少し離れて息抜きをする時間も、看病・介護生活の中の必要なプロセスだと思います。それは決して、手を抜いているということではありません。
ペットちゃんたちにとって家族の方は、一緒に暮らしてきた日々の生活の中でより介助が必要になった自分(ペットちゃん自身)を生かすために、いろんなスケジュールを調整しながら、時にはいろんな人に謝ったりお礼を言ったりしながら配慮や協力をしてもらって、自分のために力を貸してくれたと映っているのではないかなと思います。
死別という、いつの時代も、どんなに偉い人でも決して覆すことのできない別れ。それはペットとの別れに限ったことではなく、親族や友人、同僚など誰かとの死別があった時にも「もう少し話をしておけばよかったな」と誰しもが思うことではないでしょうか。
後悔があるのは自分だけではありません。誰が相手でも、どんな状況でもどんな時代でも、遺された私たちには何かしらの後悔が残る場合が多く、それはあくまで自然なものなのです。そこから何を学ぶか、なにを糧にしてこれからを生きていくかまでを含めた結果として、ペットちゃんたちは私たちの人生を輝かせてくれているのかもしれません。
後悔から自分の心を救うには、自分をほめてみて

後から冷静になってその時のことを振り返ったり、後から知った情報で「あの時こうしてあげられたのでは」と後悔をしたりする必要はありません。その時に自分が全力で考えた結果の行動を、愛するペットのためにしていたのではないですか?
ここで1つ、私たちの後悔の要因になる1つの概念についてお話ししたいと思います。
数字の「ものさし」は人の世界のもの

この本で私が好きな一節に
おとなは数字が好きだから。新しい友だちのことを話しても、おとなは、いちばんたいせつなことはなにも聞かない。「どんな声をしてる?」とか「どんな遊びが好き?」「蝶のコレクションをしてる?」とかいったことはけっして聞かず、「何歳?」「何人きょうだい?」「お父さんの収入は?」など聞くのだ。
出典:サン・テグジュペリ 小説『星の王子さま』(河野万里子 訳)新潮文庫 p.23
という部分があります。
誰かのことを知ろうとするとき、数字というものさしでその人をイメージするようになってしまい、その人の本質への関心は二の次になってしまっていないでしょうか。現代でいうと、年齢や出身校の偏差値、身長、SNSのフォロワー数…もちろんそれは大人の人間の世界ではその人のプロフィールを知るために手っ取り早い場面もあるのですが、本当に大切なことというのは「その人が大切にしていること」「どんなことに幸せを感じるか」「どんなものが好きか」など、数字では説明できないことがその人の本質を知るためには大切なことなのかもしれません。
この考えを、ペットたちの世界に置き換えてみましょう。
時間という数字の流れや数の概念というのが、ペットたちにはありません。
「お誕生日まで生きられなかった」「何歳まで生きられなかった」というのは、人が勝手に考えた時間という数字の中での目標や節目で、ペットちゃんたちにとっては「あなたといる今この時」が何よりも大切なのです。
「毎日夕方6時になるとごはんだと思ってテンションが上がる」「家族が返ってくる時間になると玄関で待っている」など、まるでその子たち自身が時間をわかっているかのような行動を取ることもありますが、それはあくまで私たち飼い主の習慣や傾向を分析して、その行動に伴ってペットちゃんたちが先回りして動き出している、というほうが正しいかもしれません。
もし、数字という概念が自分の誇りになるのであれば、それは心の宝物として持っていられれば良いですが、一方で数字が自分を苦しめてしまっているのなら、ペットちゃんたちにとってピンと来ていない概念で遺された家族が苦しんでいる必要はないと思いませんか?
飼い主としての「理想」や人間特有の「数のものさし」を手放して

「最期は私の腕の中で」と思っていても、病状が悪化して動物病院で息を引き取る場合もありますし、叶えたかった約束を果たせないままになってしまうということもあるでしょう。
一緒に生きていくための希望を持ち続けるからこそ、そこに理想は生まれます。ですが、その理想が自分自身の努力ではどうしても叶わないこともたくさんあります。
その子の最期の在り方の理想が、結果的に自分を苦しめているのなら、少しその理想を手放してみてくださいね。
そして、年齢や月齢、記念日、目標の数字…これらのような「数のものさし」が後悔の引き金になってしまっているのであれば、一度ペットちゃんたちの目線に立ってみて、彼らにとって「?」な概念に苦しむことも一旦お休みしてみましょう。
「私、よくやったよ。あの子のおかげで頑張れたよ。」と少しでも思うことができたのなら、一緒に過ごしてきた意味や、出会いから別れも含めて全て、その子との時間を肯定的に受け入れて自分の人生を彩ってくれた大切な存在だと心から思えるようになるかもしれません。
私の後悔体験記
後悔の正体を推察して、それを手放すための考え方をこうして言葉に表せるようになるまで、私も愛犬の死に直面した時にはたくさんの後悔をしてきました。後悔をしては誰かの言葉に救われたり、新しい縁があって迎えた存在に改めて教えられたりと、後悔や学びを繰り返してきています。これまで私自身が飼い犬との別れを経験する中で感じた後悔や学び。過去の記事でも掲載をしていますので、よかったらご覧ください。
愛犬の最期を看取れなかった後悔を消化できるようになるまで
 私が人生で一番初めに家族として迎えた愛犬は、ゴールデンレトリーバーの「ロック」という雄のワンちゃんでした。約30年前、地元の新聞に「子犬譲ります」と掲載されていたのを見つけて譲ってもらい、子犬の頃から一緒に育ってきました。
私が人生で一番初めに家族として迎えた愛犬は、ゴールデンレトリーバーの「ロック」という雄のワンちゃんでした。約30年前、地元の新聞に「子犬譲ります」と掲載されていたのを見つけて譲ってもらい、子犬の頃から一緒に育ってきました。
ロックは当時のゴールデンレトリーバーにしては長寿の、16歳半で生涯を終えました。お別れはそれはそれは悲しかったですし、最期は両親が看取って私自身が立ち会うことができなかったことがずっと後悔として残っていました。ずっと胸のつっかえが後悔として残っていて2年ほど経ったときでしょうか、その当時知り合った友人に亡くなった愛犬の話をしていると「ロックちゃんが由さんに最期を見せなかったのは、見せないほうがいいと思ったからじゃないのかな。きっと立ち直れなくなっちゃうと思ったのかもしれない。それは、由さんことを一番よく知っているのロックちゃんの計らいだと思って、受け入れなきゃ」と言われて、スーッと胸のつっかえが取れていくように感じました。
そうか、私のことを一番よく知っているロックが、「お姉ちゃんには旅立つ姿を見せない」と思っていた最期なのかもしれない。その姿が焼き付いて、私が立ち直れなくなってしまうと思ったのかな…と、妙に納得したのを覚えています。
自分に都合のいい解釈だと人からは思われるかもしれませんし、言葉のない動物たちからなんの根拠があってそんな推察を? と思う方もいらっしゃるでしょう。それでも、その科学的ではない解釈で後悔を消化できてしまう、ロックと私が重ねてきた時間や絆が培ってきた、誰にも説明できない根拠が私の心にはあるのです。
後悔という胸のつっかえが和らいだ私にとって、いつしかロックが長寿だったことが何よりの自慢で、誇りとなっていました。
長生きが誇りと思っていた私の心を変えた愛犬

旅立つ約1か月前のキナ。
その後迎えた、同じゴールデンレトリーバーの「キナ」という雌のワンちゃんは、3歳の終わりごろに我が家にやってきました。それから12歳半で生涯を終えるまで、実際に一緒に居られた期間は約9年間でした。
私が8歳から24歳まで一緒にいたロックは、血を分けたきょうだいも同然な存在でした。その後、27歳から35歳まで一緒にいたキナは、私自身の立場(年齢)からしても娘同然の存在でした。実は結婚して間もなかった当時の私は、なかなか子供が授からないことに不安になっていた頃でもあり、時々病院に行ってはいわゆる「不妊治療」をしていた頃でした。その後、いろんな感情の変化があり子供がいない人生を歩んでみようという風に自然に心が向くようになるまで、いつもにっこりとした笑顔でそっと寄り添ってくれたのがキナでした。
キナは本当にたくさんの病気をしました。子宮蓄膿症、肥満細胞腫、リンパ腫、腎臓病、外傷のケガでの縫合手術や腫瘍によるしっぽの断尾など、振り返れば動物病院のお世話になることが多かった、手がかかるけれど可愛い子でした。
キナを迎えたとき、すでに3歳だったことや、かなり肥満気味で胸や腰回りに信じられないほどの脂肪の塊がついていて(その後ダイエットをしましたが)、心のどこかで「ロックの時ほど一緒に居られる時間は長くないだろうな」と感じていました。それでも、一緒に暮らしてしまえば本当にかわいくて、キナがいてくれれば自然と笑顔になれるあたたかい時間をたくさんプレゼントしてもらったと思っています。
最期は腎臓病が急激に悪化して、12歳半でその生涯を終えました。キナの最期の24日間は、つきっきりの看病が続きました。両親も毎日キナに会いに来て、スタッフのみんなも補水液の点滴や看病に惜しみなく力を貸してくれました。そして迎えたキナの最期は明け方でした。息苦しそうにするキナに酸素マスクを当てながら、夜中じゅう頭を撫でて過ごしていました。3時を過ぎたころでしょうか…ほんの一瞬私が寝落ちをしてしまったそのときに、キナは息を引き取ったようです。
「私は絶対頑張れる!」と、ほとんど休まず看病をし続けていて、24日経った私の身体はかなりへとへとながらも常に気が張っている状態でした。ロックの時の後悔を繰り返さないためにと、キナの最期の瞬間には看取りたいという理想の想いが私を躍起にさせていたのかもしれませんが、体力の限界でふと眠ってしまったその時を見計らったような最期の時でした。まるで「重要なことはそんなことじゃないってロックから学ばなかったの?」と言わんばかりに、キナは私の気構えをスルリとかわして虹の橋へと旅立って行きました。
悔しかったけれど、それでも不思議とキナの時にはロックの時のような「看取れなかった」という後悔は残りませんでした。私自身ができることをやってこられたという想いや、周りの人たちの力を借りることができて、「みんなのおかげでキナは幸せだっただろうな」と思うことができたからだと思います。
掘り起こしてしまえば小さな後悔はたくさん出てくるのかもしれません。でも、ロックもキナも私の人生に必要な大切なパートナーであることはこれからも変わりませんし、家族になってくれたこと、たくさんの幸せをくれたことに感謝をして、可愛かったところ、笑わせてもらったところをたくさん話しながら、ずっとずっと家族の輪の中にいてもらいたいと思っています。
そして迎えたシニア犬との新生活

迎えたシニア犬 エルモ
「こんな悲しい思いをもう二度としたくない」「あの子以上の子はいない」と、大切なペットを亡くしたあとは誰しもが思うことでしょう。私もそうでした。現に、初代の愛犬のロックを亡くしたあとは「また犬と暮らそう」という気持ちが起きないまま4年の歳月が過ぎていました。
その後縁あって迎えたキナが、「犬と暮らすってこんなに楽しかったんだ」と思い出させてくれました。ロックとキナと、犬種は同じでも雌雄の違いや性格の違いでおもしろいところを家族で話して、先代のロックのことも明るく思い出話ができるようになるきっかけをくれたのはキナでした。
キナの火葬の日は、家族や、葬儀に立ち会ってくれたふくふくやまのスタッフのみんなに肩を抱いて背中をさすってもらいながら、大きなキナの遺影で顔を隠して思い切り泣きました。口はカラカラ、鼻水だらだら、目はブクブク、泣きすぎて強烈な頭痛。そんな経験をしても、犬がいない生活というのはなんだかとても寂しくて、「またいつか縁があれば」と心のどこかで願う日々が続いていました。
ある日、仙台市の動物保護施設の譲渡犬情報に出ていた1匹の犬と出会いました。推定10歳~12歳のシニア犬でした。ロックのことしか知らなかった昔の私は、長生きが美徳のように思っていましたが、幼少期を知らず成犬として迎えたキナと暮らして見送ってからは、「一緒に居られる時間が長いのはいいことだけれど、それがすべてではない。どう一緒に楽しく幸せに過ごすか」という考えに変わっていました。
シニアで迎えた現在の愛犬はすでに持病もあり、どのくらい一緒に居られるかはわかりません。それでも、私を必要としてくれていると感じる瞬間にこの上なく幸せであたたかい気持ちにしてもらえるのです。服薬をうまくペッと吐き出す時には、同じようなことをよくしていたロックを思い出しながら、「なんでも飲み込んでいたキナちゃんを見習いなさい!」と笑って、唾だらけの薬を拾ってまた口の中に放り込むトライをしている瞬間も、なんともうれしい時間です。
縁があって迎えた子が、我が家という環境で私たち夫婦やふくふくやまのスタッフみんなに囲まれて、穏やかな時間を過ごしていけるようにすることが、私の人生の1つの役割なような気がしています。
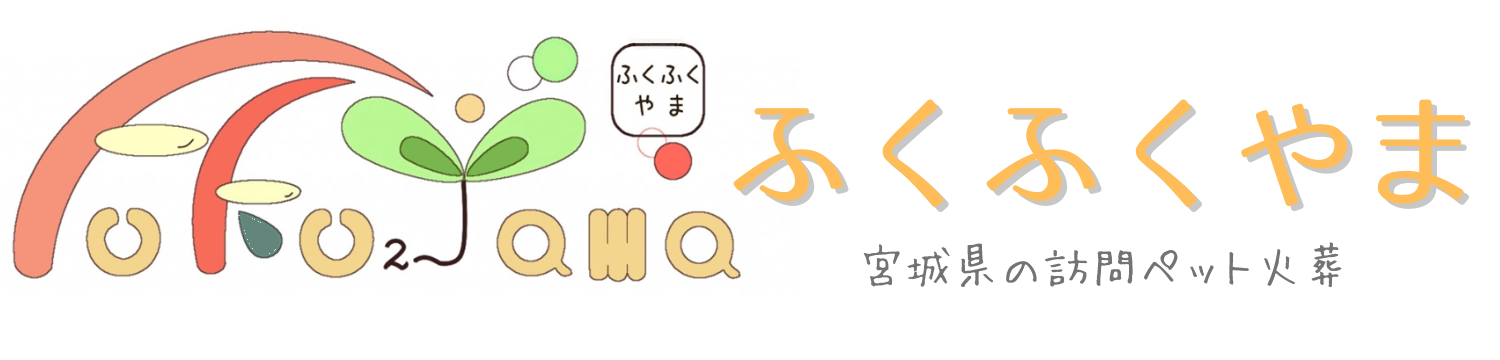
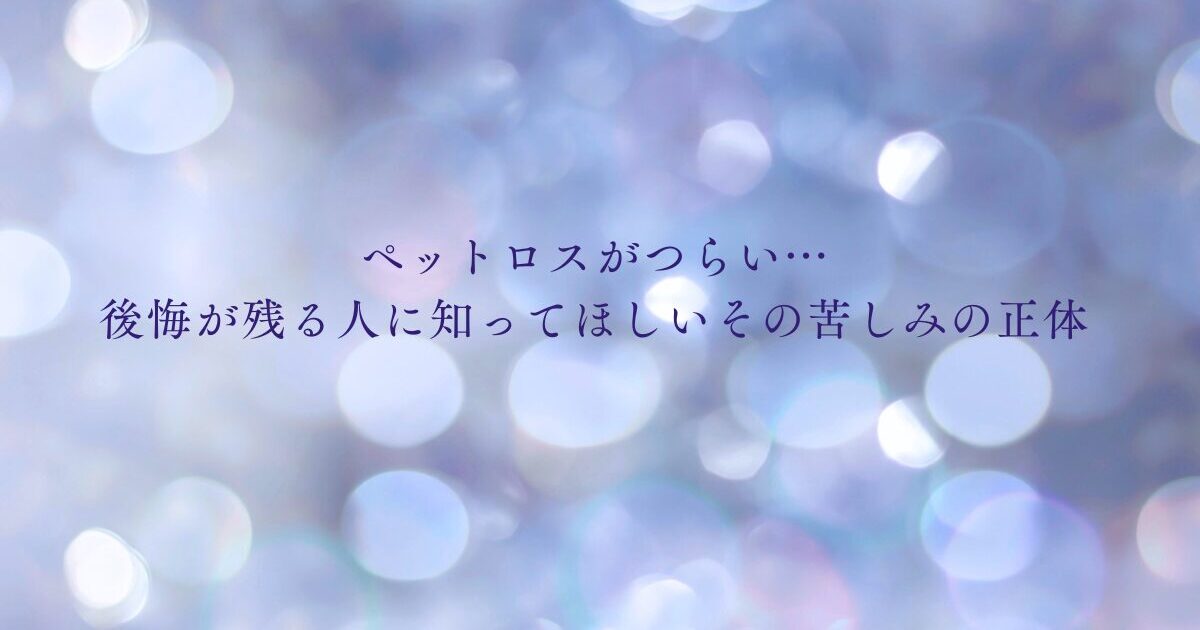



こんにちは。2年半以上たっても毎日毎日泣いています。乗り越えるつもりもないけど、たまにペットロスをググってはやめて。初めて心に響いたのがこちらでした。ありがとうございました。エルモ幸せだね
コメントをいただきましてありがとうございます。同じ気持ちのかたのお心に届いたとのお声、とても励みになります。一緒に暮らした子、今も一緒に暮らしている子、みんなに私自身が幸せをもらっている気がしています
こんにちは。最近私の不注意で愛犬が亡くなりました。
ネットでこちらのサイトを見つけ、愛犬の名前がロックと同じでなんか勝手にご縁を感じました。
毎日自分を責めて泣いてる日々です。
本来ならまだまだ元気で一緒に過ごせたはずなのにと思うとたまらなく辛いです。
すみません。周りには心配かけたくないので、気持ちの吐き出しをこちらでしてしまいました。
この度はお気の毒さまでございます。
きっとロックちゃんは、M様の笑った顔ややさしいお顔が好きだったかと思います。責めて悲しい気持ちが強いかと思いますが、ロックちゃんへの「ありがとう」の気持ちや「大好きだよ」の愛情を
たくさん伝えていただけたらなと思います。
どうか体調を崩さないよう、暖かくしてお過ごしくださいませ。