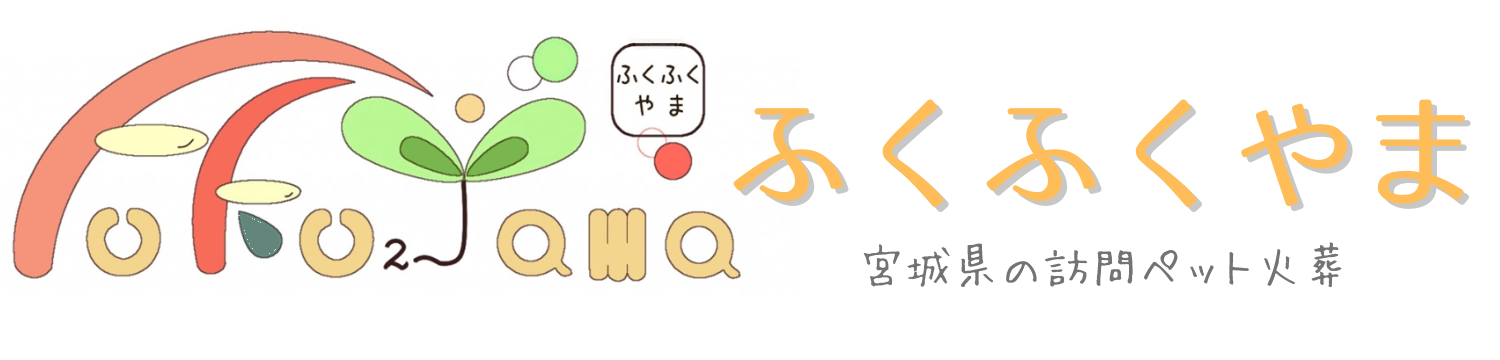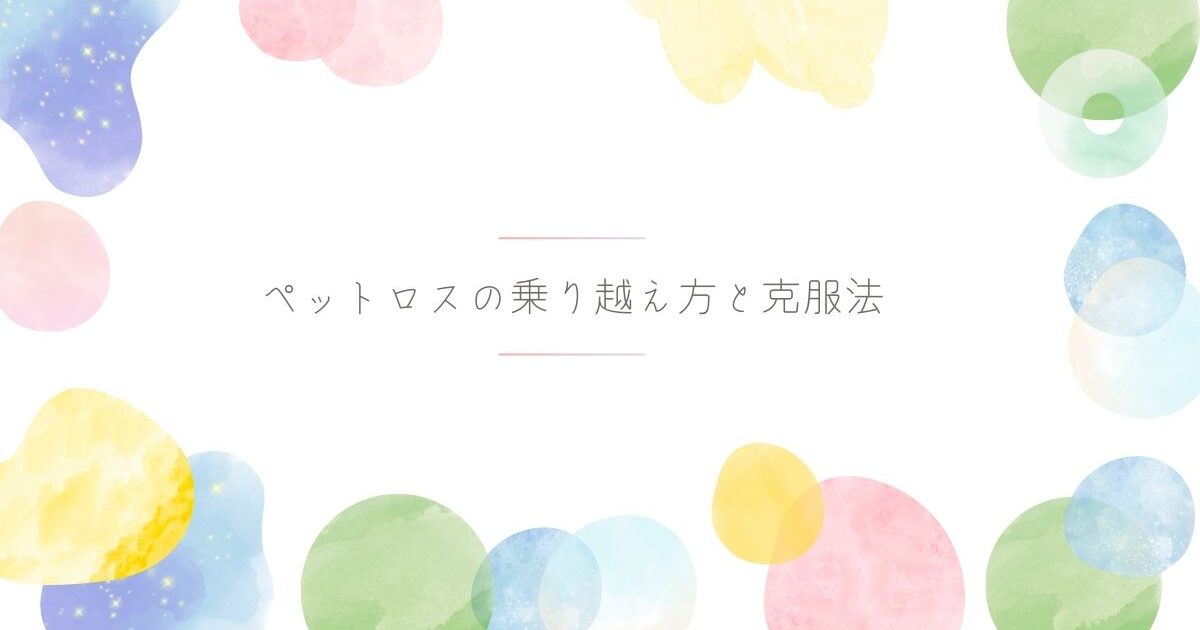最終更新日 2025.2.26. by fukufukuyama
いつの日か訪れるペットの死。ペットが大切な存在になればなるほど「ペットロス」と呼ばれるペットの死に遭遇した時の悲しみがより深くなることでしょう。
ペットの寿命は人に比べて短く、避けては通れない出来事です。ペットを家族同然に愛情を注ぎ暮らす飼い主にとって、いざ別れを迎えた際には悲しみや喪失感が押し寄せることは想像に難くありません。深い悲しみの中、ペットロスの状態からの乗り越え方について悩まれている方も多いのではないでしょうか。
悲しみを抱えることは当然のことです。
本記事では、ペットロスの乗り越え方が分からず悲しみから抜け出せないつらい日々から、“ペットの死”を受け止め、
過ごした時間を大切な思い出として捉えていけるために、「ペットロスの乗り越え方と心の整理法」について考えていきたいと思います。
また、深い悲しみの中にいるペットロス状態の当人だけではなく、その周囲の人が乗り越え方を理解することで、心を寄せた対応ができるヒントとなり得るかもしれません。
ペットロスとは?~ペットの死によって起こる症状と原因~
ペットロスとは、愛情注ぎ可愛がっていたペットを失った後に感じる深い悲しみや喪失感を指します。もちろん犬・猫だけではありません。うさぎ、鳥、ハムスター、爬虫類、魚類、家族同然の愛情を注ぐペット達と過ごす人であればどんな動物種との別れにおいてもペットロスの悲しみが訪れることはあり得ます。
ペットロスの感情はペットが家族の一員として日常生活に深く根付いているほど、ペットの死や別れに直面した際に強く現れる傾向があります。ペットロスの症状は人それぞれですが、その多くは立ち直れないほどの悲しみ、無力感、そして喪失感を伴うことが大きな特徴です。これらの感情はしばしば長期間にわたって続くことがあり、食欲不振や不眠など身体的な影響も相まって、日常生活に影響を及ぼすことも少なくありません。
残念なことに一部の理解のない人からは、「たかがペットが死んだくらいでそんなに悲しむなんて」と、ペットロスは人間の死別体験より軽く扱われることがあるのが現状です。
思いを向ける対象が人であれペットであれ、その深い愛情に違いがない以上ペットロスの喪失感への寄り添い方について理解も深めていくことが大切です。
弊社のペット葬儀の際にも「自分の親の葬式よりも泣いた」とお話になるご家族様もいらっしゃいます。ただまっすぐに愛情を注ぎ、自分を信じてくれていた愛犬。気ままな態度と裏腹に、人の気持ちをよく理解してつらい時には寄り添ってくれた愛猫。一緒に生きてきた時間は、人と動物との垣根を越えて深い絆となるのだということがよく分かります。
ペットロスの一般的な症状
ペットロスの一般的な症状としては、まず心理的な影響が挙げられます。これは具体的に、悲しみや落胆、罪悪感、孤独感などが含まれ、日常生活に影響を及ぼすことがあります。また、うつのような長期的な精神的状態に発展することもあるため、注意が必要です。落ち込みや虚無感などのようなうつ状態というのは、日常で暮らしている誰しもがなる可能性がありますが、そこを乗り越えるには周囲の協力や本人の気力、医療の力なども必要で、立ち直れない状態が続くとうつ状態からのうつ病に発展してしまう可能性もあります。
さらに、身体的な症状も現れることがあります。例えば、食欲不振や睡眠障害、慢性的な疲労感などが挙げられます。これらの症状は、ストレス応答として体が反応していることが原因です。ペットとの日々のルーティンが崩れることで、生活のリズムが乱れることも影響しています。
社会的な側面も無視できません。ペットロスを経験した人は、周囲の人々との交流を避けたり、孤立感を感じたりすることがあります。特にペットとの時間を共有していた家族との気持ちの温度差などもあり、関係が変化することもあります。これにより、さらに孤独感が増すこともあり得ます。
症状は人それぞれ異なり、深刻さも様々ですが、適切な家族のサポートやカウンセリングを受けることで、心の健康を保ちながら、少しずつ日常生活を取り戻していくことが可能です。
ペットロスが起こる原因
ペットロスが起こる原因は、ペットと飼い主の間に築かれる深い絆や愛情、そしてそのペットが家庭や日常生活に与える影響に大きく関係しています。ペットは多くの飼い主にとって、家族の一員やかけがえのないパートナーです。ペットとの生活を通じて得られる日課や感情的な支えも、その存在が失われたときにペットロスの大きな原因となります。毎日の散歩や食事の時間、遊びのひとときなどが日常生活の一部となっているため、それらが突然失われると、生活のリズムや心の安定が崩れ、喪失感を強く感じることがあります。
また、ペットが病気や老衰で徐々に衰えていく姿を見ることも、心理的に大きなストレスとなり、ペットロスの一因となることがあります。ペットの最期を看取る際の選択や決断は、飼い主にとって非常に辛いものであり、これが後悔や罪悪感を引き起こすこともあります。ペットの死が予期せぬものであった場合や、看病や介護に多くの時間と労力を費やしていた場合もその喪失感は一層深まることがあります。
また、一部の研究ではペットロスは人間の死別体験よりも対処困難であるという報告もされているようです。それはペットロスに特有な点として以下のことが挙げられるためです。
- 人が亡くなった時に比べて周囲の人々に辛さや悲しみを理解してもらえないことが多い。
- 治療や安楽死の選択を迫られるなど飼い主がペットの生死を判断する場面がある。
- 家から逃げ出してしまった等、生死が分からないまま曖昧な別れを経験する場合がある。
家族同様の存在なのに、動物であるがゆえに周囲の人々に理解してもらえないことや、安否の確認が取れないことが悲嘆を長引かせることもあります。その子が苦しまないためにと最善の方法として安楽死の選択をした飼い主でも、命の期限を自分の判断で決めたということに罪悪感が強く生じたりもします。人の死もペットの死もそれぞれに特有の悲しみがあります。そもそも人であれ動物であれ大切な存在を失ったことに変わりはなく、喪失の辛さを比べること自体おかしな話かもしれません。
以上のように、ペットロスは単なるペットの死という出来事以上に、喪失感による様々な要因が重なり合うことで身体や心に深刻な問題となるのです。
ペットロスを乗り越えるには~立ち直れない時の心の整理法~
ペットロスを乗り越えるには、自分の感情を素直に受け入れることから始めましょう。
感情を抑え込むことは、後々の心の健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、辛く悲しい時には涙が出るままに泣いても良いのです。
ペットロスに対するケアは、周囲が能動的に働きかけるよりも、当事者がありのままの感情を表現できるような環境を整えて、その感情を周囲の人が傾聴の姿勢をもって受け入れることが有効です。
ペットロスを乗り越え克服するための日常生活の工夫
ペットロスを経験した後、日常生活に戻るためには無理に普段の生活に戻ろうとするのではなく、自分のペースで時間をかけて心の傷を癒すことが大切です。
日常生活の中で小さな目標を設定することが有効です。例えば、毎日の散歩や軽い運動を取り入れることで、身体を動かすことが心の健康に良い影響を与えます。音楽や読書、アロマテラピーなどでリラックスする時間を作るのも良いでしょう。さらに、友人や家族とのコミュニケーションを大切にし、社会との繋がりを意識的に持つようにしましょう。人との交流は、孤独感を和らげ、新しい視点を得る機会を提供します。少しずつ自分自身を取り戻し、焦らずに進んでいくことが大切です。
1.心の整理をするためにたくさんお話をしよう
ペットとの思い出を振り返る中で、悲しみや喪失感に対する正直な感情を自分自身が受け入れることは、心の癒しにもつながります。感情の日記をつけることや、ペットへの感謝の気持ち、共に過ごした時間の中での思い出を文章にしたり、思い出を写真や動画で整理することも効果的です。これにより、心の中にある複雑な感情を少しずつ解消し、自分の感情を整理していくことができます。ペットとの楽しかった時間を振り返ることで、心の中でのペットの存在を肯定的に捉え、前に進むためのステップとなります。
また、心の整理には他者とのコミュニケーションも役立ちます。家族や友人とペットについて語り合うことで、感情を共有し、支え合うことができます。ペットロスの経験を持つ人々が集うグループに参加するのも一つの方法です。共通の体験を持つ人々と交流することで、孤独感を和らげ、前向きな気持ちを取り戻す手助けとなります。友人や家族と死別したペットの思い出を語り合うことも、孤独感が和らぎ、気持ちが軽くなることがあります。同じペットを愛する者同士であれば、共感を得やすく、心の支えになるでしょう。
ただし、あまり他者に感情の共有を期待しすぎても自分が傷ついてしまう場合もあります。同じ家族でも、「いつまで泣いてるんだ」と、悲しみに寄り添うよりも叱咤激励をする方もいますし、ペットに対する考え方の違いで、その言葉の1つ1つに自分が傷ついてしまうこともあります。
少し気持ちが落ち着いたらペットを失った後の新しい生活を考えることも、心の整理の一環です。ペットがいない生活に徐々に慣れ、新しい日常を築いていくことが、ペットロスを乗り越える前向きな一歩を踏み出す助けとなります。
2.ペットの祭壇を作り供養をする
悲しみを受け止め、きちんと供養することは、愛するペットへの感謝の気持ちを表し、心の整理を進めペットロスを克服するための重要な過程です。
供養の方法は様々で、一般的にはペットの遺骨をペット専用の墓地に納める、家の庭に埋葬する、また骨壷に納め手元供養として自宅で供養するなどの方法があります。近年では、死別したペットの火葬後の遺骨を分骨ケースに納めたり、アクセサリーに加工して身に付けて供養する方もいます。
供養を行う際は一般的に、花やお供え物を置いて、亡くなったペットを偲ぶ場を設けることが挙げられます。また、ペット専用の霊園や納骨堂を利用する方法もあります。これらの場所では、遺骨を安置し、定期的にお参りすることができます。供養を通じてその子の存在を心に留めつつも、感情を整理し、前向きな気持ちを持つことができるでしょう。また、その子を想い偲んで手を合わせた時には、自分の感情を無理に押さえ込まず、自然体でいることが重要です。涙を流すことも、笑顔で思い出を語ることも、すべて供養の一部です。愛情と感謝の気持ちを持って、自分にとって最も心地よい方法で愛するペットを偲ぶことでより深い癒しを得ることができ、心の安らぎにつながることでしょう。
3.専門カウンセリングの活用
カウンセリングは、ペットロスの悲しみを乗り越えるための効果的な手段の一つです。
専門のカウンセラーは、ペットロスの当事者の感情に寄り添い、個々の状況に応じたサポートをしてくれます。ペットロスカウンセリングを受けることで、自分の感情を整理し、適切に表現する方法を学ぶことができます。多くの人は、ペットを失った直後に感情を封じ込めてしまいがちですが、カウンセリングでは秘密が守られた心の安全が保たれた環境で解放することができます。
カウンセリングの形式は様々で、対面型、オンライン型、グループ型などがあります。それぞれの形式にメリットがあり、自分に合ったスタイルが選べます。例えば、対面型では直接的なコミュニケーションが可能で、オンライン型は移動の手間が省けるため忙しい人に向いています。グループ型は、同じような経験を持つ他の人々と共感し合うことで、孤独感を和らげる効果があります。
カウンセリングを受ける際には、自分のペースで進めることを心がけましょう。無理に早く立ち直ろうとする必要はなく、じっくりと自分の気持ちに向き合うことが大切です。また、カウンセラーとの信頼関係を築くことも重要です。信頼できる相手に自分の感情を開示することで、より深い癒しが得られるでしょう。カウンセリングを通じて、自分の感情を理解し、ペットを失った悲しみを乗り越える力を少しずつ養うことができます。
4.医療機関を受診する
ペットロスは時間の経過とともに改善に向かいますが、私生活に影響が出て、重度な身体的・精神的症状が現れてきた際は然るべき医療機関においての受診をおすすめします。
例えば、ペットロスによって引き起こされる可能性のある不安障害やパニック障害、うつ病のような症状は、専門的な治療が必要です。これらの症状に対して、心療内科や精神科医であれば、カウンセリングを含め、場合によっては薬物療法などの処方を通じて、心の負担を軽減してくれるでしょう。
ペットロスによる心身の症状に焦点を当て、ストレスマネジメントや自律神経の調整を行い、不眠や食欲不振、心身症などの症状が現れた場合、適切な治療とカウンセリングにより、身体的なバランスを取り戻すお手伝いをしてくれることと思います。
ペットロスの克服は、時には適切な医学的介入が必要な場合もあります。改善の段階を踏まえて症状に応じた治療が、心の健康を取り戻し、再び日常生活を送れるよう、心理的・身体的サポートを提供してくれるでしょう。
5.悲しみをエネルギーに変えてみよう
ふくふくやまは、愛犬を失った時の悲しみで探し回った仏具屋さんで、当時はまだかわいい仏具が無いというもどかしい思いから、うちの子らしいかわいいペット仏具を作ろうと悲しみをエネルギーに変えて創業しました。
弊社をご利用いただくご家族様でも、自分自身の経験を活かしてペットロスケアカウンセラーの資格を取得し、今はペットロスのかたの心を支えるお仕事をしていらっしゃるかたもいます。
また、愛犬や愛猫を想って趣味の手芸を極めていった結果、羊毛フェルト人形の作家になった方もいらっしゃいます。
そうやって、悲しみに沈んでしまうのではなく何か自分の経験を誰かの支えになる形に思い起こしていくことが、自分自身の癒しにもなっていくのかもしれません。
~愛猫の骨壷カバー作製がきっかけで作家に~
弊社でお世話になっている骨壷カバーの作家のかたは、愛猫ちゃんが亡くなったときに火葬場のひんやりとしたお骨壺に入って遺骨が返ってきたことで心を痛め、もともとお裁縫が得意だったためご自身で骨壷カバーを作られたそうです。それがきっかけで国内縫製にこだわった骨壷カバーの会社を立ち上げ、今ではペットを亡くされたたくさんの方の心の支えとなる骨壷カバー屋さんになっています。
6.新しい子を迎える
暫くは犬や猫などのペットとの関わりに抵抗がある場合もあるかと思いますが、気持ちが落ち着いてきたら、ペットとの思い出を新たな形で生かす活動を始めるのも一つの方法です。
ペット愛好家のコミュニティに参加したり、ボランティア活動を通じてご自身の経験や思いを活かしつつ、他のペットや飼い主と交流することは、心を癒し、前向きな気持ちを育む手助けとなります。
新たにペットを迎えることも、ペットロスを克服する一つの方法です。しかし、これには十分な準備が必要です。まず、自分の心が新しいペットを受け入れる準備ができているかどうかを確認し、無理に急がず、自分のペースで進めることが大切です。人から勧められて迎え入れてしまうのも良くありません。ペットロスの感情がまだ強く残っている場合、新しい子を迎えることが逆にストレスになることもあります。つい、失った子と目の前に居る子を比較してしまうこともあるかもしれません。その場合、ご自身も新しく迎えられた子もつらい思いをしてしまうかもしれません。自分の正直な気持ちを大切にまずは、心の整理がある程度進んでいることを確認しましょう。 新しい子との生活を想像し、どのような関係を築くことができるかを考えてみましょう。これにより、新たに迎えるペットとの生活が心の癒しとなるかもしれません。
ペットロスを無理に克服しないのが1つの乗り越える方法
ペットロスを経験することは、愛するペットを失った人にとって非常に辛いものです。悲しみや喪失感は自然な感情であり、それを感じること自体が心の癒しのプロセスの一部です。無理に「元気にならなければ」と思うことは、逆に心の負担を増やすことがあります。自分のペースで感情を受け入れ、時間をかけて癒やしていくことが大切です。
ペットロスを克服することが目的ではなく、心の中でどのようにペットとの思い出を大切にしながら、新しい日常を築いていくかを考えることがペットロスを乗り越えるための近道です。
“ペットロスになってしまうのは、愛犬や愛猫を心から大切に思っていた証拠です。”
無理に乗り越えようとすることなどないのです。
愛するペットが与えてくれた思い出や教えてくれた感情、亡くなった後に遺してくれたもの…これらをきちんと受け止め心を整理することで、「ずっと大好きだよ」「ありがとう」など別れたペットへのプラスな想いが増えていくことと思います。
人によって悲しみの感じ方が違うように、ペットロスを受容し改善するまでの道のりや克服方法も人それぞれです。ペットロスを受け入れるのは平坦ではない大変な道のりで、どれほど時間がかかるかもわかりません。それでも、ペットとの思い出は、決して消えることなく、これからもずっとあなたの人生の一部として生き続けます。無理に克服しようと頑張らず、少しずつ自分の想いと向き合っていくことが、ペットとの別れを乗り越える支えとなるでしょう。
ペットロス~私の乗り越え方
この記事をご覧になっている方は、今まさにペットロスに悩み、どのように乗り越えたらと苦しんでいる方がおられることかと思います。
可愛がってきたペットの死を迎えるということは、想像を絶する悲しみに直面するということを、私自身も体験して思い知りました。
「高齢になったからいつかお別れの時が来るのかもしれない…。」
と、心の中ではなんとなく覚悟のようなものをしていましたが、訃報を聞き、死と直面した時には胸が痛み、身を切られるような思いをした経験があります。
その時から長い年月が経った今、私自身ペットロス とどのように向き合い、乗り越えてきたのかを振り返ってみました。
ペットロスに悩まれている方の乗り越える方法の参考のひとつになればと願います。
我が家は動物好きの父の影響で、家にペットがいないことはありませんでした。犬や猫、ウサギ、小鳥やアヒル…。ペットの存在はいつでも家族に笑顔と癒しを与えてくれていました。
小さい頃はペットが亡くなると、その時には号泣し、悲しい感情はあったものの「次は何を飼うの?」と、いう具合にその子がいないことへの悲しみは直ぐに薄れて新しい子を迎える期待や喜びの気持ちの方が強かった記憶があります。
かけがえのない子との出逢いと別れ
私が小学校高学年になると、父は一匹の子犬を迎え入れ、子犬の食事や運動、しつけなどを含め、私が責任を持って育てるように言いました。愛情に応えるように子犬も私にとても懐いてくれて、きょうだいのような、親友のような存在で何をするにも何処に行くのも一緒でした。
私の進学で、ずっと傍にいてくれた愛犬と離れる時は両親と離れるよりつらかったことを覚えています。家族が私に代わり、可愛がってくれていましたが、その頃既におばぁちゃん犬だった愛犬は私の帰省を待つことなく旅立っていきました。
死に立ち会えなかったこと、何もしてあげることができなかった自分を責めました。
優しく、頼るような瞳でいつも私を見ていたその表情ばかり目に浮かび、泣いてばかりいました。
幼い頃のように、数日後には新しい子を迎える気持ちなど到底持つことなど出来ず、後悔の思いばかりが心の中に広がっていました。
思い出と悲しみとの共存
愛犬を亡くし、立ち直れない毎日を過ごし塞ぎこんでいた私を気遣い、友人が「虹の橋」という優しい詩を教えてくれました。作者は不明ですが、世界中で語り継がれている有名な詩です。
インターネットで「虹の橋」と検索すれば全文を見ることができますが、天国に向かう道の途中に虹の橋がかかっていて、亡くなったペットはまずそこへ行くのだそうです。
そこには、草原が広がっていて、病気で亡くなったペットたちも、ここでは元気いっぱいに走りまわっている場所。
私たち飼い主が命をまっとうして天国へ向かうとき、虹の橋で愛するペットと再会でき、一緒に橋を渡ることができると綴られています。
愛犬と「また逢える…」胸が熱くなり、涙が溢れました。私はこの詩に出逢い少しずつ悲しみを癒すことができました。
辛く悲しい思いをするのはたくさん愛していたからと思うようにしました。
私もたくさんの愛情をもらったことを思い出しました。
いつも傍で寄り添い、人生の大切なひと時を共に歩んでくれたことに感謝し、「ありがとう」と思うようにしました。
新たに迎えた家族
少しずつ心が整理され、亡くなった子が私の心の中で生きていると思えるようになり、自然と笑顔も戻ってきた記憶があります。
愛犬の死を経てペットロスのつらい経験から二十年、もうあの時の思いはしたくないと新たにペットを迎え入れる気持ちさえなかったところに、引き取り手のない子犬を飼ってもらえないかとの話がありました。家族に相談すると、家族もあの時の私と同様につらい思いを抱えていた経験があるので断るつもりでいましたが、どうしても飼い主が見つからない状況に、今の私なら大丈夫かもしれないと家族を説得し、迎えることとなりました。

すると不思議と別れた子をたくさん思い出し、
「あの子にしてあげられなかったことたくさんしてあげよう」と、思うようになり、今の子も旅立った子も一層愛おしく思えるようになりました。
私にとって新しい子を迎えた今が本当の意味でペットロスを乗り越えたのかもしれません。
心が元気になる時間はお一人お一人で異なります。回復までに長い時間がかかるほど、不安は募ります。
どれだけ長く悲しみの中にいらしたとしても適切な心のケアをすることで悲しみは癒えるものです。
克服には時間かかるものです。
つらい時は一人で悩まれずに誰かに頼っていいのです。
思い切り泣いてもいいのです。
我慢せず、ご自身の抱えてらっしゃる感情や想いを素直に出すことで少しずつ心の痛みや悲しみが和らいでくるかと思います。
悲しみはいつか慈しみへと変わる時が来るはずです。